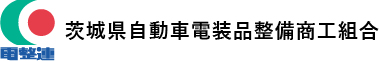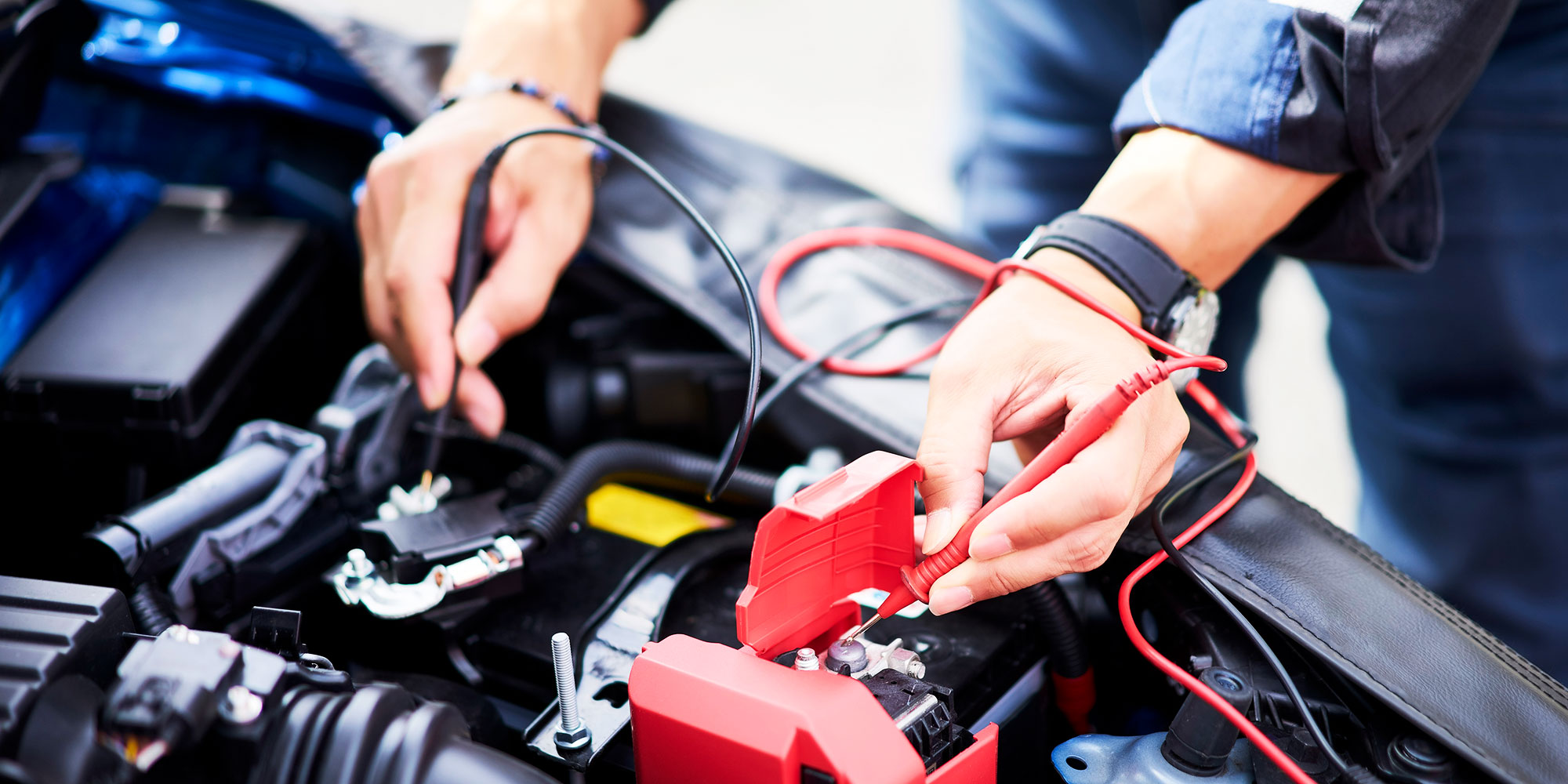
組合の概要
組合の概要
理事長挨拶
一言ご挨拶を申し上げます。
日頃は関係者の皆様には、当組合の活動に大変なご協力、ご理解を頂き、誠にありがとうございます。
今日、あらゆる産業や社会構造の大きな変化、市場環境の変化等により、我々自動車整備業界にも大きな変革の波が押し寄せてきております。
そこで、茨城県自動車電装品整備商工組合の概況につきまして、下記のとおり申し上げます。
立地環境
私たちの茨城県は筑波山や霞ケ浦、そして総延長190kmに及ぶ海岸線など豊かな自然と温和で暮らしやすい環境に恵まれています。
又、つくばエクスプレス鉄道が東京秋葉原に直結しており、常磐自動車道、北関東自動車道、首都圏を囲む圏央道の3本の高速道路と一体となって世界につながる鹿島港、茨城日立港等や成田空港、茨城空港などと結び、陸、海、空の広域ネットワークを形成しています。
更には最先端の科学技術を擁する筑波研究学園都市や高度な物づくり産業が立地するなど大きく発展し続ける可能性を有しております。
組合の歴史
私たち茨城県自動車電装品整備商工組合は昭和36年に、当時設立していた全国の24組合の代表が一堂に参集し会議され、自動車電装品整備業界唯一の中央団体として「全国自動車電装品整備組合連合会」という任意団体を創設しました。
以来、運輸省(現国交省)の指導の下、業界基盤の確立を理念として健全なる発展に努めて参りました。
昭和46年に各県において組合の法人格、すなわち商工組合に改組する動きが活発になり、そして整備組合連合会から新たに運輸省(現国交省)専管による整備商工組合連合会(電整連)を設立し、自動車電装品整備業としての社会的地位を確立しました。
そして高度に発展してきた我が国の「くるま社会」において欠くことの出来ない自動車整備の中の電気・電子・カーエアコン関係を中心とした専門分野の整備を担当するプロの技術集団として重要な社会的役割を果たして参りました。
自動車産業のパラダイム
今日、自動車整備業界を取り巻く環境は大きく変化し、まさに自動車産業のパラダイムシフトが進んでおります。
すなわち「くるまのスマホ化」「ロボット化」であり、車と人工知能(AI)の融合が進むと自動運転技術が進化して、無人で完全自動運転の車が登場してきます。
これに伴って国交省は道路運送車両法の一部を改正する法律「特定整備認証制度」を令和2年4月1日より施行されました。
この特定整備認証制度が自動車の車検・点検整備の在り方を大きく変えることになりました。
特定整備は分解整備の対象だった原動機や制動装置など7つの装置に自動運転装置を追加し、その名称を分解整備から特定整備に変更したのであります。
このことは先進運転支援システムのみならずレベル3以上の自動運転技術も視野に入れており、高度化する車両技術に対応した新たな点検整備制度が始まることとなりました。
特定整備の対象となる電子制御装置の状態が点検出来るよう整備記録簿に「OBD(車載式故障診断装置)車検の診断の状態」を追加するということが新たな点検基準となるのです。
組合の方針
この特定整備認証は我が業界の得意とする電気・電子の分野において国家資格として取得することができることになりました。
当組合の会員が既に取得している、又これから新しく資格取得するであろう電気装置整備士が特定整備認証工場資格の第一歩となります。
茨城県自動車電装品整備商工組合は、この運転支援技術や自動運転技術の進化と普及により我々電気装置整備事業者は、今後ガラス修理事業者への整備士資格取得に向けて支援し、県自動車整備振興会との連携強化を図りながら、又車体整備事業者と協力しながら、来るべく整備需要に応え、事業発展の為、全力を傾注することが重要であります。
今や車社会は電子制御装置を中心として、ますます高度化する技術、多様化する顧客ニ ズ並びに自動車に関する環境問題等に対応する為に、組合員の技術のレベルアップ、企業の近代化、経営体質の改善強化等を指導推進して、課せられた社会的責務を遂行すべく努力を続けて参る所存であります。
組合組織
| 理事長 | 入江 元 |
|---|---|
| 副理事長 | 須鎌 泰成 内田 寛 |
| 理事 | 永井 靖彦 針谷 栄一 藤田 裕司 井坂 義明 佐川 真治 吉波 一真 |
| 監事 | 石井 一江 藤田 光美 |